| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 2023 | 2024 | 2025 |
- 2011年11月16日
24年度予算要望書 提出  11月8日(火)、公明党川口市議団は 「24年度予算要望書」を岡村市長に提出しました。
11月8日(火)、公明党川口市議団は 「24年度予算要望書」を岡村市長に提出しました。
大項目14(施策の柱)、小項目約200(要望事項)となります。
市議団として市民要望を聴取しながら討議を重ね、多様な住民ニーズを的確に捉えた予算編成を最小の経費で最大の効果を得られるように、市民生活の向上と市政の発展を願って要望書を完成させました。
1.徹底した行財政改革の推進
2.災害対策の強化
3.防犯対策・交通安全対策の強化
4.子育て支援の充実
5.高齢者・障害者福祉施策の充実
6.安心を提供する医療・介護体制の充実
7.市民サービスの充実で住みよいまちづくり
8.文化・芸術・スポーツ振興で賑わいのある豊かなまちづくり
9.教育改革の推進
10.人権擁護と生命尊重のまちづくり
11.不況対策・中小企業振興策・雇用対策等の推進
12.都市基盤整備の推進
13.斎場建設
14.地球高温化対策の推進- 2011年10月12日
9月定例議会 一般質問に登壇  9月12日、一般質問を行ないました。
9月12日、一般質問を行ないました。
今回の行政に対しての質問及び提案は、以下の通りです。
1.特定規模電気事業者(PPS)利用で行財政改革の推進を
2.バス利用者のための地域ターミナル整備について
3.環境センターの飛灰・溶融飛灰の安定処分について
4.ストックヤード建設事業等について
5.ご当地ナンバープレートの導入について
6.在宅医療の相談体制強化について
7.妊婦歯科健康診査の個別受診実施について
8.高齢者の健康増進に健康器具の拡充を
9.保育料徴収基準額表の見直しについて
10.安全・安心な歩行空間の確保に複合型無電柱化の推進を
11.東本郷運動広場での迷惑行為による近隣被害について- 2011年9月22日
第2回八ッ場ダム建設推進全体協議会に参加  8月24日、永田町の憲政記念館で開催された、第2回八ッ場ダム建設推進全体協議会に参加しました。
8月24日、永田町の憲政記念館で開催された、第2回八ッ場ダム建設推進全体協議会に参加しました。
挨拶はじめ、これまでの経緯・取組み状況の説明、今後の活動方針(案)について等協議、各関係団体の決意表明等も行われました。
「大会決議」
今秋までに、国がダム本体工事の中止を撤回しない場合は訴訟を含め国の責任を徹底的に追求する。
また、国に代わり共同事業者である1都5県が所要の手続きを経て、ダム事業を完成させる等。
八ッ場ダム再検証
9月13日、治水・利水の両面でダム建設が最良と国土交通省関東地方整備局が評価し、建設再開に向け動く可能性もでてきた。
埼玉県は八ッ場ダムが必要
●治水面では、利根川は5~6年に1度は、堤防すれすれまで水がくるところがある。
スーパー堤防での河川改修も下流域ほど堤防際まで家があるため難しく、ダムで水量を減らすことが求められている。
平成13年の台風15号の洪水では、加須市などで堤防決壊につながる漏水が生じた。
●利水面では、過剰に地下水を汲み上げていたため、地盤沈下が発生してしまった。
地下水に頼っていたため安定水利権の確保に遅れ、今、水利権を河川法に基づき市町村に水道水を供給しているが、この中には八ッ場ダムを前提にした暫定水利権が29%もあり、その水量は、約160万人分の水道水に相当する。
また、利根川水系では、平成になって、6回渇水で10~20%の取水制限をしている。
川口市の平成22年度の配水量は59、494、296㎥で、その9割が県水であり、その県水のうち9割が利根川水系のものである。
今、世界的な異常気象であり、渇水にも備える必要があるのではないか。- 2011年6月8日
川口グリーンセンターで芝生のポット苗移植法を採用 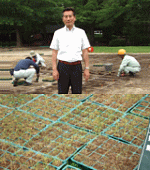 6月7日、川口グリーンセンターの「わんぱく広場」で芝生のポット苗移植による鳥取方式を採用することになり、ティフトン苗、植付けを視察しました。
6月7日、川口グリーンセンターの「わんぱく広場」で芝生のポット苗移植による鳥取方式を採用することになり、ティフトン苗、植付けを視察しました。
鳥取方式とは、ニュージーランド人ニール・スミス氏が提唱する芝生のポット苗移植法で、ティフトン芝をポットの中で育て、1㎡当たり4束を田植えのように植えていきます。
苗も安価で除草剤や農薬を使用しないため低コストで環境にもやさしく、専門業者でなくても施工可能なところがいい。
この鳥取方式を以前より、公明党川口市議団は、学校の校庭や公園などの広場に採用するべきと要望してきました。- 2011年5月20日
市長へ緊急要望書を提出  国難とも言われる東日本大震災の被害状況から、市民の皆様が自然災害に対する脅威をあらためて認識し、震災対策の重要性を求められております。
国難とも言われる東日本大震災の被害状況から、市民の皆様が自然災害に対する脅威をあらためて認識し、震災対策の重要性を求められております。
同時に、更なる住みよい川口市の実現を望む市民の声を受けました為、5月17日、公明党川口市議団で岡村市長へ「安心・安全な住みよいまちづくりを求める緊急要望書」を提出いたしました。
【災害対策の強化】
◆川口市の液状化防止対策等、 防災計画の見直し
◆防災無線の整備
◆災害時の情報通信対策
◆避難所の再点検と鍵の管理や備品の見直し
◆本庁舎の建て替え(災害対策本部の機能充実)
◆耐震診断・耐震補強の助成金の拡大
◆集中豪雨対策(雨水貯留管の設置・河川整備)
◆被災者生活再建支援法等の円滑運用
【子育て支援施策の充実】
◆子ども医療費通院分の中学3年生まで無料化
◆保育所対機児童の解消
◆学童交通指導員の存続
【福祉施策の充実】
◆赤山歴史自然公園等の早期実現
◆障がい児の学童保育(放課後の居場所)の拡充
◆単身高齢者世帯の見守り体制の強化
◆市営納骨堂の拡充(合葬式納骨堂の設置)
◆国民健康保険制度の県への一元化
【住みよいまちづくりの推進】
◆川口駅(中距離電車の停車等)の整備
◆西川口駅周辺に運転免許センターの設置
◆ミニバスの導入でルート拡充(利便性の向上)
◆自転車専用レーンの設置拡充
◆公共下水道未整備地域に早期敷設
◆区画整理事業の更なる推進- 2011年5月15日
こどもの日 記念街頭演説  5月5日こどもの日を記念し今年も川口駅東口で街頭演説をおこない下記報告をさせて頂きました。
5月5日こどもの日を記念し今年も川口駅東口で街頭演説をおこない下記報告をさせて頂きました。
私は、児童に対する身体的虐待や育児放棄などの問題が深刻化しているため、その対策の一環として、相談業務の強化を図るため家庭児童相談員の増員を平成22年9月定例議会で質問し川口市の家庭児童相談員の少なさを指摘しました。
その結果、本年4月より4名体制になりました。- 2011年4月16日
高齢者・交通不便地域の交通対策 - 私が提唱しているオンデマンド交通の導入に向け始めの一歩が踏み出されます。
オンデマンド交通はバスとタクシーの中間に位置している予約制の乗り合い交通で、ドアtoドアに近いため高齢者にとっては病院や買い物などに便利に利用できます。
また近年、東京大学が開発した管理システムは、安価で優れており、購入や維持にかかる費用を従来技術の20分の1程度に縮小させており、さらに希望時刻への遅延もありません。
私は平成23年3月定例議会において、交通不便地域及び高齢化社会の交通対策について市の基本的な考え方を質問しました。
さらに、今後の交通対策として、オンデマンド交通などについて、タクシー事業者などとの意見交換を行うべきであると、求めたところ、タクシー事業者等に対するヒアリングや意見交換等についても行っていくとの答弁をいただき、オンデマンド交通導入に向け一歩前進! - 2011年4月1日
市長へ要望書を提出  東日本大震災による福島第一原発の影響から、川口市内の新郷浄水場で3月22日に採取した水道水に、放射性ヨウ素が食品衛生法に基づく乳児の飲用に関する暫定的な指標値の100ベクレル/キログラムを超過する120ベクレル/キログラムの濃度が測定されたことから、「安心・安全な水道水の供給を求める緊急要望書」を公明党市議団で岡村市長に提出しました。
東日本大震災による福島第一原発の影響から、川口市内の新郷浄水場で3月22日に採取した水道水に、放射性ヨウ素が食品衛生法に基づく乳児の飲用に関する暫定的な指標値の100ベクレル/キログラムを超過する120ベクレル/キログラムの濃度が測定されたことから、「安心・安全な水道水の供給を求める緊急要望書」を公明党市議団で岡村市長に提出しました。
【市長への要望内容】
1.毎日、各浄水場の検査をし、放射性ヨウ素の測定値を公表すること。
2.測定値が、食品衛生法に基づく乳児の飲用に関する暫定的な指標値を超えた場合即座に公表し、乳児がいる家庭を優先に、対策を講じること。
3.非常事態に備え、今後考えられる様々な対策を速やかに講じること。- 2011年3月25日
3月定例議会 一般質問に登壇  3月9日をもちまして3月定例議会が閉会いたしました。
3月9日をもちまして3月定例議会が閉会いたしました。
私は2月25日、任期最後であり8回目となる一般質問に登壇させて頂き以下のような質問をさせて頂きました。
1.がん予防について
(1)がん検診推進事業について
(2)子宮頸がん予防ワクチン接種について
2.交通施策について
(1)高齢者・交通不便地域の交通対策について
(2)日暮里・舎人ライナーの延伸について
3.教育と子育て支援について
(1)子どものトイレの衛生教育と環境改善について
(2)妊婦向けメールマガジン(めるママ)の配信について
(3)留守家庭児童保育室の対象児童と指導員体制について
4.市民サービスについて
(1)狭あい道路でのごみ収集について
(2)中央図書館のビジネス支援コーナーの充実について
5.循環型社会の構築について
(1)インクカートリッジ里帰りプロジェクトについて
(2)レアメタルの回収システムと回収技術について
6.自然エネルギーの有効活用について
7.地域経済活性化について
(1)地元小規模を含む中小企業の育成について
(2)小規模を含む中小企業の研修会などへの参加費用の負担補助について
8.地域問題について
(1)狭い道路での火災および各種救助等について
(2)赤井地内の雨水排水の解消策について- 2011年3月17日
地中熱利用ヒートポンプシステムの実証実験を視察 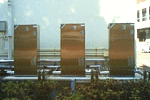 2月3日、春日部市役所の地中熱利用冷暖房システムの実証実験を視察しました。
2月3日、春日部市役所の地中熱利用冷暖房システムの実証実験を視察しました。
このシステムは地下の温度が年間を通じて一定であるのを利用して冷暖房を効率的に 行えるシステムで、地下を暖房の際の熱源に冷房の際の放熱先として利用するため省エネ効果、二酸化炭素排出量抑制につながるほか、放熱用室外機が無いことによる騒音と排熱がないため、都市部のヒートアイランド現象の抑制にもなります。
今後本市でも、常時使用できる地中の自然エネルギーの有効活用を考えるべきではないか。- 2011年1月21日
リサイクルフラワーセンターを視察  平成23年1月14日、県南都市問題協議会の私が所属している環境問題研究部会で、蕨戸田衛生センターのリサイクルプラザとリサイクルフラワーセンターを視察しました。
平成23年1月14日、県南都市問題協議会の私が所属している環境問題研究部会で、蕨戸田衛生センターのリサイクルプラザとリサイクルフラワーセンターを視察しました。
リサイクルフラワーセンターでは、家庭から排出する生ごみを再生資源として堆肥にし、花の苗を生産しており、市民が分別して家庭で一定程度まで堆肥化を進められた生ごみを使用しており、市民と協働でごみの減量化と資源化を図っていました。
また、専用ごみバケツに入れて持ち込むと花苗と交換でき参加者も増えているそうです。
本市でこの仕組みを行うことは難しいようですが循環型社会や、ごみ焼却量削減を考えると、一部の生ごみを堆肥化することも検討した方が良いのかもしれません。
搬入センターを決め、破袋分離機等を設置すれば、ごみ袋ごとの搬入が可能になります。
しかし堆肥化は有効な方法ですが、作った堆肥の使用先の問題があるため大量の堆肥化は難しいと考えます。
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 2023 | 2024 | 2025 |
